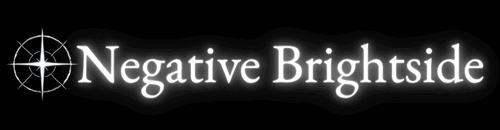「将来何をしたいか」と問われて「起業なんて無理」と即答する日本人は多い。
なぜなのか?
それは選択肢を想像できないからだ。
雇われることしか頭にない。
この思考パターンの背後には何があるのか。
なぜ日本人は「誰かに雇ってもらう」以外の生き方を思い描けないのか。
それは偶然ではない。
構造的な問題だ。
奴隷根性の歴史的構造と「責任回避願望」の正体
日本人の雇われ思考の根源は、封建制度にある。
江戸時代の身分制度、明治以降の天皇制、そして戦後の終身雇用制度。
形を変えただけで、本質は同じだ。
常に誰かの下につき、決められたルールに従う。
現代の転職市場も、この延長線上にある。
「転職の自由」があると錯覚しているが、結局は「どの主人に仕えるか」を選んでいるだけだ。
支配構造は何も変わっていない。
より深刻なのは、日本人が「責任を取らない自由」を求めた結果として、この従属を選択していることだ。
起業には責任が伴う。
失敗すれば自分の責任になる。
それが怖いから、雇われの檻に逃げ込む。
自由には責任が付いてくる。
日本人はその責任を恐れるあまり、自ら首輪をはめることを選んだ。
そして「これが安定だ」「これが現実的だ」と自分を納得させている。
現代に現れる奴隷根性の症状と集団催眠
この奴隷根性は、日常のあらゆる場面に現れる。
有給を取ることに罪悪感を覚える。
残業代を請求することに躊躇する。
「会社に迷惑をかけられない」と本気で思っている。
なぜか?
自分の権利を主張することが「わがまま」だと刷り込まれているからだ。
「みんな一緒なら安心」という集団催眠も深刻だ。
隣が奴隷なら、自分も奴隷でいい。
これが同調圧力の正体だ。
みんなが残業していれば、自分も残業する。
みんなが転職していれば、自分も転職を考える。
思考を放棄して、群れに従う。
最も歪んでいるのは、従順であることが「性格の良さ」と同義になっていることだ。
上司に逆らわない部下が「優秀」と評価される。
理不尽に耐える社員が「我慢強い」と褒められる。
思考停止がモラルになっている。
従順は本当に美徳なのか
「日本人は勤勉だ」と言われる。
しかし、それは本当に美徳なのか。
自分で考えることを放棄し、与えられた作業をひたすら続ける。
それを「勤勉」と呼ぶなら、工場のロボットも勤勉だろう。
違いは何か。
日本人の「勤勉さ」の多くは、思考停止の結果だ。
「なぜこの仕事をするのか」
「この会社に価値があるのか」
「もっと良い方法はないのか」
こうした疑問を持つことすら、「協調性がない」と批判される。
疑問を持たず、文句を言わず、黙々と働く。
それが「良い社員」とされる社会。
これは勤勉ではない。
訓練された従順さだ。
企業はこの従順さを都合よく利用する。
「みんなで頑張ろう」
「会社のために」
「お客様のために」
美しい言葉で包みながら、労働者の思考を停止させる。
そして労働者も、その方が楽だから従う。
選択の自由という幻想
現代の日本人は「自由」だと思っている。
転職の自由、消費の自由、居住の自由。
確かに選択肢はある。
しかし、それは幻想だ。
与えられた選択肢の中から選ぶことを「自由」と呼んでいるに過ぎない。
選択肢そのものを疑うことはしない。
「雇われること」という前提を疑わない限り、どれだけ転職を繰り返しても、本質的には何も変わらない。
主人が変わるだけだ。
この構造に気づいた者だけが、幻想の存在を疑うことができる。
しかし、気づく者は少ない。
なぜなら、気づかない方が楽だからだ。
思考することには責任が伴う。
従うことには責任がない。
日本人は後者を選び続けている。