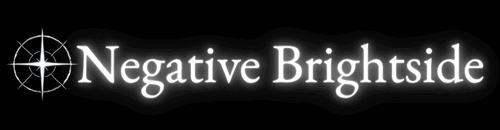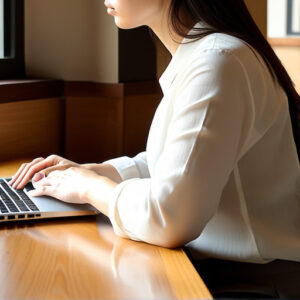「成功か失敗か」
「ポジティブかネガティブか」
「努力するかしないか」
なぜ世の中は、こんな単純な二元論で溢れているのか。
人生は白黒で割り切れるほど単純ではない。
成功と失敗が同時に存在し、努力しても報われない構造があり、正解のない選択を迫られる。
それが現実だ。
しかし、社会は複雑さを許さない。
なぜだろうか。
思考停止を量産する社会システム
答えはシンプルだ。
複雑な思考は、社会の効率を下げるからだ。
考えてみてほしい。
現代社会が求める「理想的な人間」を。
素直に指示に従い、与えられた役割を疑問なく果たす労働者。
単純な成功モデルを信じ、消費を続ける顧客。
白黒はっきりした価値観で、迅速に判断を下す管理者。
複雑に考える人間は、このシステムにとって邪魔なのだ。
だから社会は、幼い頃から二元論的思考を植え付ける。
「良い子か悪い子か」
「勝ち組か負け組か」
「正解か不正解か」
挫折を単純化する自己啓発産業
本来、挫折は人を複雑な思考へと導くはずだ。
失恋、失業、病気、家族の死。
こうした経験は「なぜ?」という問いを生む。
単純な答えでは説明できない現実と向き合わざるを得なくなる。
しかし、ここに自己啓発産業が入り込む。
「挫折を乗り越えた私の成功ストーリー」
「失敗から学ぶ7つの教訓」
「どん底から這い上がる方法」
複雑で個別的な苦しみが、売れる商品に加工される。
答えのない問いが、安易な解決策にすり替えられる。
本当は「乗り越える」でも「這い上がる」でもない、ただそこに在るだけの痛みもある。
しかし市場は、そんな曖昧さを許さない。
全ては「ビフォー・アフター」の物語に変換されなければならない。
成功体験という麻薬の配給システム
この社会は、一部の人間に「成功体験」を与える。
生まれつきの容姿、経済的な環境、時代の幸運。
これらの要因で「成功」を手にした人間は、それを「努力の結果」として語ることを求められる。
他の人間に希望を与え、システムを維持するためだ。
「私にできたのだから、あなたにもできる」
この言葉は、構造的な不平等を覆い隠す。
個人の努力という物語で、システムの欠陥を見えなくする。
複雑さを許さない効率化の暴力
現代社会は、あらゆる場面で「効率」を求める。
採用面接は数分で判断される。
SNSの投稿は一瞬で評価される。
人間関係すらマッチングアプリで効率化される。
複雑さを理解する時間など、誰にも与えられない。
だから人々は、単純な基準にすがりつく。
「成功者の特徴10選」
「失敗する人の共通点」
「幸せになる5つの習慣」
メディアも教育も、この単純化に加担する。
複雑な現実より、分かりやすい物語が売れるからだ。
特権の不可視化という巧妙な仕掛け
最も巧妙なのは、この構造が「特権」を見えなくすることだ。
恵まれた環境で育った人間ほど、その恵みに気づかない。
それが「普通」だと思い込む仕組みが、社会全体に組み込まれている。
「外見は関係ない」と言わせるのは、外見差別の存在を隠すためだ。
「お金で幸せは買えない」と言わせるのは、経済格差を正当化するためだ。
特権を持つ者自身に、特権の存在を否定させる。
これほど効果的な支配はない。
世代を超えて再生産される思考の檻
この二元論的思考は、世代を超えて受け継がれる。
親は子に「正しい生き方」を教える。
学校は「正解」を求める。
企業は「成果」を評価する。
どこにも、複雑さと向き合う場所はない。
グレーゾーンで立ち止まることは許されない。
こうして、思考停止のサイクルは永遠に続く。
二元論という支配の道具
人生は、成功か失敗かで測れない。
努力の有無で決まらない。
無数の要因が絡み合い、予測不可能な結果を生む。
それが現実だ。
しかし、この複雑な現実を認めることは、既存のシステムを脅かす。
だから社会は、二元論という単純な枠組みを押し付け続ける。
二元論は、支配の道具だ。
複雑さを奪い、思考を停止させ、現状への疑問を封じる。
そして今日も、この構造は静かに、しかし確実に、私たちの思考を蝕んでいく。