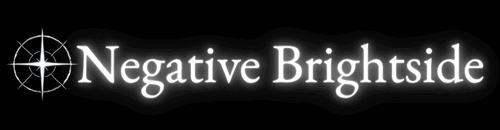「人生こんなもんだよ」
この台詞を口にする人間の表情を観察したことがあるだろうか。どこか得意げで、悟ったような雰囲気を漂わせている。まるで人生の深淵を理解した賢者のような顔つきだ。
だが、その表情の裏側にあるのは、思考の完全な停止である。
この台詞は、本質的な問題と向き合うことを放棄した個体が、自らの思考停止を「人生経験」や「大人の余裕」として美化するための装置に過ぎない。そして現代社会は、この種の思考停止を積極的に称賛する構造になっている。
右往左往から諦めへの美しい物語
多くの個体は、人生において一定のパターンを繰り返す。自己啓発本を読み漁り、「今度こそ変わる」と決意し、数週間後には元の生活に戻る。次に流行の成功法則に飛びつき、また失敗する。転職を繰り返し、人間関係でも同じトラブルを起こし続ける。
この右往左往の過程で、彼らは重要な気づきを得る機会を何度も与えられる。なぜ同じパターンを繰り返すのか。根本的に何が間違っているのか。どこで思考を停止しているのか。
しかし、その気づきと向き合うことは苦痛を伴う。自分の思考の浅さ、判断の甘さ、現実認識の歪みを受け入れることになるからだ。
そこで彼らが選択するのが、「諦めの哲学化」である。「結局、人生なんてこんなもんだ」「完璧な人間なんていない」「みんな同じような悩みを抱えている」。こうした言葉で、自らの思考停止を正当化する。
最も巧妙なのは、この諦めを「人生を知った大人の余裕」として演出することだ。若い頃の理想主義を卒業し、現実を受け入れた成熟した個体。そんな物語を自分に与えることで、思考停止に美しい意味を付与する。
適応戦略としての思考停止
ここで誤解してはならないのは、思考停止それ自体が必ずしも悪いわけではないということだ。
個体にとって、深く考えることは常にエネルギーを消耗する行為である。すべての問題について本質まで掘り下げて考えていたら、日常生活が成り立たない。ある程度の思考停止は、個体の生存戦略として合理的な側面もある。
問題は、その思考停止を「知恵」や「悟り」として美化することだ。
「人生こんなもんだよ」と語る個体の多くは、偶然にもその思考停止戦略がそれなりに機能した経験を持っている。大きな失敗をせずに済んだ、それなりに安定した生活を送れている、周囲からも「現実的な人」として評価されている。
こうした偶然の適合者が、偶然の不適合者(思考停止戦略がうまく機能しなかった個体)に対して優越感を抱き、自らの戦略を正当化する。「あいつは考えすぎるんだ」「もっと肩の力を抜けばいいのに」「人生、そんなに深刻に考えなくても」。
だが、これは単なる適応戦略の違いに過ぎない。思考停止が機能する環境にたまたまいた個体が、思考を必要とする環境にいる個体を見下しているだけの構図だ。
社会が求める思考停止の美化
現代社会は、思考停止を積極的に美化する装置を多数用意している。
「大人になる」とは、理想を捨てて現実を受け入れることだとされる。「成熟」とは、深く考えることをやめて、与えられた役割に満足することだとされる。「人生経験が豊富」とは、多くの挫折を経て、最終的に諦めることを覚えた状態だとされる。
この美化装置は、結果的に社会システムの維持に貢献している。深く考える個体が増えれば、現状の矛盾や不合理を指摘する声が大きくなる。構造的な問題を構造的な問題として認識する個体が増えれば、システムの変更を求める圧力が高まる。
意図的かどうかは別として、「人生こんなもんだよ」という諦めは、こうした圧力を緩和する安全弁として機能している。個体の不満や疑問を、個体の未熟さや考えすぎの問題として処理することで、システム自体への批判を回避する。
結果として、真に考える個体は少数派に留まり、大多数は思考の外観だけを装いながら、実質的には与えられた枠組みの中で右往左往を続ける。そして最終的には、その右往左往すらも「人生の豊かさ」として肯定的に解釈する。
私たちが照らすべきは、この美しく装飾された思考停止の正体である。諦めを哲学と勘違いする個体たちの、静かな自己欺瞞の構造である。
「人生こんなもん」ではない。ただ、考えることをやめただけなのだ。