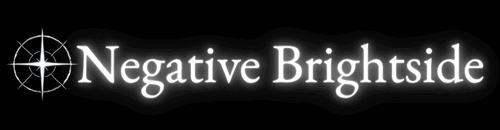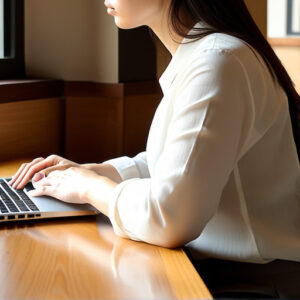「コップに水が半分入っています。あなたはどう思いますか?」
この手の質問に出会うたび、私は心底うんざりする。
決まって出てくるのは「半分も残っている」と答える人はポジティブで前向き、「半分しかない」と答える人はネガティブで後ろ向き、という薄っぺらい分類だ。
だが、ちょっと待って頂きたい。
「半分しかない」と答えた人間は、事実をそのまま述べただけではないのか。
コップの容量に対して水が不足している状態を、ありのまま認識しているだけだ。
一方で「半分も残っている」と答える人間は、なぜ「残っている」という表現を選ぶのか。
まるで不足している現実を「豊富さ」の表現で覆い隠そうとするかのような物言いだ。
なぜ「現実認識」がネガティブ扱いされるのか
この構図の奇妙さに気づかないだろうか。
現実を直視する者がネガティブ扱いされ、現実に化粧を施す者がポジティブと称賛される。
まさに倒錯した価値観だ。
ただ、誤解しないでほしい。
私はポジティブな思考そのものを否定しているわけではない。
現実を受け止めた上で前向きに行動する姿勢は、むしろ尊敬に値する。
問題なのは、思考を放棄したポジティブ風味が社会全体を覆い尽くしていることだ。
貧困は「まだ生きているだけマシ」、過労は「仕事があるだけありがたい」、理不尽な扱いは「勉強になる」。
すべてが「見方次第」という魔法の言葉で片付けられ、分析も改善も放棄される。
だが、コップの水が半分しかないなら、それは単純に水が足りないという事実だ。
のどが渇いている人間にとって、その水では不十分かもしれない。
植物に与えるには少なすぎるかもしれない。
こうした具体的な問題を「ポジティブに考えよう」で解決できるとでも言うのか。
思考停止のポジティブ風味が社会を蝕む仕組み
思考停止の「半分も残っている」という発想は、結局のところ現状維持を正当化するだけだ。
水を足すという発想も、より大きなコップに変えるという発想も生まれない。
ただ「今のままでも大丈夫」という自己欺瞞を続けるだけだ。
こうして社会は、問題を問題として認識する能力を失っていく。
構造的な欠陥があっても「見方次第」で片付けられ、改善への動機は削がれる。
そして現実を指摘する者は「ネガティブ」のレッテルを貼られ、沈黙を強いられる。
私たちに必要なのは、コップの水が半分しかないという事実を事実として受け入れる勇気だ。
その上で、水を足すのか、コップを変えるのか、それとも別の解決策を探すのかを考える知性だ。
現実逃避を「ポジティブ」と呼ぶのは、もうやめにしないか。
現実を受け止めた上で前向きに行動すること。それこそが真のポジティブなのだから。