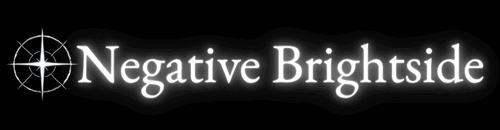SNSでも日常会話でも、「思考停止」という言葉を見聞きすることが増えた。
周囲に流される人、何も考えずに選択する人、疑問を持たない人。
そうした存在に対して、
「こいつ、思考止まってんな」
「もっと考えろよ」
と批判する光景が、珍しくなくなっている。
たしかに、“考えない”ことで問題が生まれる場面はある。
無意識に差別を助長したり、権力に従ったり、不正を見逃したり──
思考の不在が、社会にとっての危機となることもあるだろう。
だが、ここで一度、問い直してみたい。
「思考停止だ」と断じるその視線は、どこから来ているのか。
「考えなくても済む人間」は、確かにいる
思考停止という状態は、多くの場合「考えなかった本人の怠慢」として批判される。
だが現実には、“考えずに生きられる環境”に置かれた人間も存在する。
- 家庭に恵まれていた
- 学校で空気を読むことを自然に学んだ
- 職場や社会で波風立てず適応してきた
そうした人々は、「問い」を抱く必然性がなかった。
疑問を持つきっかけも、考えなければならない圧力も与えられなかった。
言い換えれば、“考えなくても生きていける構造”のなかにいただけだ。
このことをもって、「だから仕方がない」と擁護するつもりはない。
だが、「思考しない状態=ただの怠け」と断じるには、あまりに粗雑である。
思考とは、“構造を問う”ことから始まる
本当の思考とは、目の前の判断だけでは終わらない。
「なぜ自分はそう考えたのか?」
「その考えは、どんな環境や言語、教育によって形成されたのか?」
──そうした“前提”そのものを遡る問いが含まれる。
他人の言動に疑問を持つのは簡単だ。
けれど、自分の“問いの出発点”まで引き返すには、想像以上の根気がいる。
「ちゃんと考えてるつもりだった」
「自分は流されないタイプだと思っていた」
そうした前提そのものが、社会や教育によって与えられた枠組みの一部かもしれない。
「他人の思考」を測ろうとした瞬間に、思考は鈍る
誰かに対して「お前は思考停止している」と言い切れる時、人は一種の安心感に浸っている。
その判断によって、自分の側が“考える者”に位置づけられるからだ。
だが、他人の思考の深度や誠実さを、外側から断定できる保証はどこにもない。
- なぜその選択をしたのか
- なぜ疑問を抱かなかったのか
- どんな背景があったのか
そうした要因は、言葉の外側にこそ潜んでいる。
それらを想像する努力もせずに、「考えてない奴だ」と決めつけるのは、
自分自身の問いを止めてしまう行為でもある。
思考とは、問い続ける姿勢そのもの
ここで一つ、はっきりさせておきたい。
思考は、何かの“正しさ”にたどり着くことではない。
むしろ、「その正しさはどこから来たのか」を問い続けることにある。
- 自分の価値観
- 自分の判断基準
- 自分の言葉
それらすべてを、「本当に自分のものか?」と疑ってみる。
このプロセスを繰り返すことが、唯一“思考している”と言える状態なのかもしれない。
自分もまた、構造の中にいる
この記事を書いている私自身も、
誰かの思想に触れ、他人の言葉を引用し、構造の中で生きている。
思考とは、常に他者との相互作用のなかにある。
完全に独立した“自分の考え”など、幻想にすぎない。
それでも──
自分の目で見て、自分の足で立ち、自分の頭で問うという行為には、意味がある。
それは、流れに抗うというより、一度立ち止まってみるということだ。
だから、こう問うてみよう
誰かの言動を見て、「考えてないな」と感じたときこそ──
まずは、自分自身に問いを返してみる。
「その評価は、どこから来たのか?」
「自分は、どこまで考えているのか?」
「思考しているという自負が、逆に思考を止めていないか?」
問いは、他人ではなく、まず自分に向けるものだ。
そうしてようやく、「考える」という営みが始まる。
最後に
“考えているふり”をして他人を叩くことも、
“何も疑わずに流される”ことも、
どちらもこの社会のなかに日常的に存在している。
大事なのは、どちらの側に立つかではない。
むしろ、**「自分は今、どこに立っているのか?」**を、静かに問えるかどうかだ。
他人の停止を笑う前に、
まずは自分の足元が止まっていないかを、確かめてみる必要がある。
自分自身の思考の限界を、誰よりも雄弁に物語ってしまう。