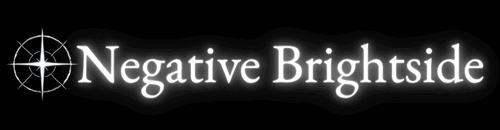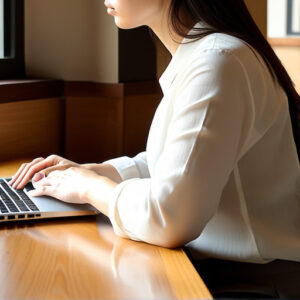「やればできる」「明日を変えるのは今日の自分」「今ここに集中すれば、人生は変わる」——
よく目にする自己啓発本のフレーズだ。
どれも正しいように見えるし、ポジティブな力に満ちている。けれど、なぜだろう。
それを読むたび、妙な違和感が残る。気持ち悪さと言ってもいい。
その正体は、言葉の裏側にある“前提”だ。
言葉は届くふりをしている。だが、そこに読者の輪郭は入っていない。
それは「再現不能な成功」を前提にしている
自己啓発本に登場するエピソードの多くは、いわゆる「成功体験」だ。
だが、それが再現可能であるとは限らない。というより、多くは再現不能だ。
成功した人間が語る“変われた理由”には、本人ですら気づいていない「偶然の適合」が含まれている。
・家庭環境が安定していた
・努力を支える体力があった
・環境の変化に適応する性格だった
・誰かが支えてくれた
そういった要素が揃っていたからこそ、変われた。
つまり、もとから“変われる素地”があった人間が、あとから「自分の努力のおかげ」と再解釈しているにすぎない。
「動ける人間」しか想定されていない
自己啓発の多くは、「読者が動ける」という前提で書かれている。
そこに、生育歴・トラウマ・うつ・経済的困窮・障害・気質の差などは織り込まれていない。
「変われない人間」がなぜ変われないのか——
その問いに一切触れないまま、「変われなかったのは努力が足りなかったからだ」と暗に刷り込む。
つまり、“効く前提”を持つ者だけが効き目を感じ、
効かない者には無力どころか、有害に作用する。
自己責任という暴力的構造
自己啓発の本質は、静かにこう囁く。
「変われなかったのはあなたのせい」
この構造に、読者が気づかないまま取り込まれていく。
ポジティブな言葉に見せかけて、「努力しなかった者への罰」を正当化する論理がそこにある。
だが本来、変化とは「構造に組み込まれること」ではない。
適応できない理由があった人間に、「適応できる者の論理」で裁きを下す——
これが、自己啓発というジャンルに隠された暴力性だ。
救われるのは、元から準備ができていた人間だけ
そもそも、自己啓発の言葉が効く人間とはどういう存在か。
- ある程度の自己肯定感がある
- 環境が比較的安定している
- 目標を設定できる力がある
- 動機づけに外部の言葉を必要としている
つまり、「言葉を受け取る準備ができている人」だけが、この種の本に救われる。
準備ができていない人間には、何も届かない。
効かない人を「切り捨てる」構造に気づけ
違う。
問題は、その言葉の構造そのものにある。
「効く前提の人間にしか効かない言葉」を、
あたかも“誰にでも通用する真理”のようにパッケージして押し売りする。
その欺瞞こそが、最大の問題だ。
努力という言葉が排除の装置になるとき、
それはもはや“希望”ではない。
届かない言葉は、信じなくていい
届かなかったのは、あなたのせいじゃない。
その言葉が、最初からあなたを想定していなかっただけだ。
「変われなかったのは努力が足りなかったから」
そんな理屈を、真に受けなくていい。
届かないものを、届くふりで信じる必要はない。
必要なのは、ちゃんと自分の足元を見ること。
変わらない日々の中にも、構造はある。
それを暴き出すところからしか、本当の変化は始まらない。