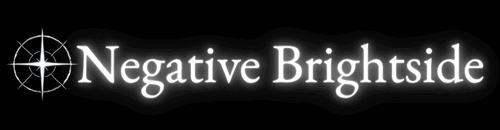「多様性」という言葉は、なぜこれほど都合がいいのか。
誰もが肯定されたように感じられ、否定も批判もできない。
自分を守る免罪符にもなり、相手を“認める側”に立つことで、やさしい人間を演出できる。
中身が空っぽでも構わない。掲げるだけで、「対応した」ことになる。
だが問題は、こうした個人の言葉遊びではない。
本質は、この言葉が使われている構造にある。
多様性がうたわれるたび、制度は一つずつ後退していく。
自由に選べる社会のなかでは、結果の責任がすべて個人に押しつけられる。
「あなたが選んだんですよね?」という一言で、政治は手を引く。企業も支援を断つ。
すべては“あなたらしさ”のせいにできる。
自由はある。選択肢もある。
だが、支えるものがない。
それが今の構造だ。
かつては規範が強すぎたが、そこには制度と支援があった。
今は「自分らしく生きて」と言いながら、つまずいた瞬間に個人を見捨てる社会になっている。
「違っていていい」と言えば、他人に干渉しなくて済む。
「あなたはあなたのままで」と言えば、何もしなくて済む。
それが“尊重”の名で正当化されていく。
そしてこの構造は、決して“少数派”だけを放り出しているのではない。
多数派――これまで社会のレールに沿い、「正しい人生」を歩んできたとされる人々もまた、支えられる理由を失い、沈黙のなかで孤立していく。
困っていないことにされ、助けを求める隙すらない。
“多様性”の陰で、誰もが「自分らしく苦しむしかない社会」が、静かに出来上がっている。
SDGs。ジェンダー平等。DE&I。
掲げた瞬間に満足し、実態は空白のまま。
助けられる人は増えず、ただ記号として処理されるだけだ。
多様性は、誰も救っていない。
ただ、誰も救わなくて済む社会をつくっている。
それが、この言葉の本当の役割だ。
『多様性は、ひとを救うこともある。だが――』
誰もが「そのままでいい」と言われる時代になった。
それに救われた人間もいる。
黙って生きるしかなかった者が、ようやく声を持てるようになった。
「違っていていい」という言葉は、時に暴力を止め、孤独をほどく。
だが、忘れてはならない。
その言葉の裏で、支援は静かに引き下げられている。
制度も、責任も、「自己選択」の名のもとに後退している。
尊重とは、「もう干渉しない」という言い訳にもなりうるのだ。